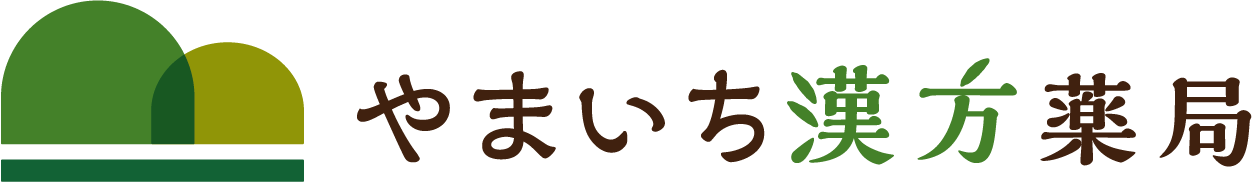こんにちは。
2025年は花粉の飛散量は多いという予報が出ています。
今年の花粉飛散量は平年比1.5倍以上と予想され、過去最高だった一昨年に匹敵し、ほぼ全国的に要注意レベル(1平方センチメートル当たり2000個)を超えたと見られています。
外出する機会も増えた今、花粉症対策は重要です。
抗ヒスタミン薬を服用する方も多いですが、眠気や集中力・思考力の低下を引き起こすことがあり注意が必要です。漢方薬はそのような心配が少なく、しかも各個人の症状や体質に合わせた対応が可能です。

花粉症ではサラサラした水っぽい鼻水が多いタイプと、乾燥傾向で頑固な鼻閉のタイプ、また、その中間など様々なタイプがあります。中医学では、鼻汁の色、質、量から、鼻の症状の特徴を弁別するほか、体全体の状態を見て漢方薬を選択します。まずは「寒」か「熱」かを見分けることが大切です。
サラサラした水っぽい鼻水のタイプには、中医学的には「肺」を温める漢方薬を用いることで症状を軽減させます。
逆に、鼻閉、黄色っぽいネバネバした粘稠な鼻水、温まると症状が悪化するタイプには、熱(炎症)が強いと考えて、炎症を鎮める漢方薬を用います。
温める漢方薬
・小青竜湯:アレルギー性鼻炎に用いられる代表薬で、水様性鼻汁、くしゃみが主体です。
・麻黄附子細辛湯:小青竜湯に近いですが、冷えや倦怠感が強くみられる場合に。
水様性鼻汁と鼻閉には、「肺」を温める漢方薬に、鼻通りを改善する「辛夷」が配合したものを用います。
・葛根湯加川芎辛夷:鼻水と鼻づまりが混合しているタイプに。
炎症を鎮める漢方薬
・鼻淵丸:蓄膿症、鼻づまり、鼻炎に。
・辛夷清肺湯:粘り気のある黄色い鼻水、鼻づまり、蓄膿症にも。
・荊芥連翹湯:熱による痒みを伴う慢性鼻炎や蓄膿症に。
症状は変化していきます。標治(対症療法)の漢方薬はずっと同じものを同じ量で飲み続けるのではなく、変化により加減しながら、場合によっては漢方薬の変更も必要な場合もあります。大事なのは「寒」か「熱」かを間違えないことです。
一方で、普段から飲んでおくと良い漢方薬もあります。本治(根本治療)の漢方薬です。
中医学では、花粉症の症状が強く現れる人は、主に「衛気不足」の体質であると考えています。「衛気」は、体の表面(皮膚や鼻、のど)をバリアのように覆い、花粉やウイルスなどの外敵から身を守る役目をしていると考えています。「衛気」の働きを回復することで、症状の軽減が期待できます。
「衛気」の充実は、何も花粉症だけでなく、病気やアレルギーを起こさない健やかな体質づくりに役立ちます。これが根本治療と考えています。
・玉屏風散:「衛気不足」の代表薬で、日本では「衛益顆粒」として売られています。「衛気」を補うとされる黄耆が多く配合されています。
日常生活で気を付けることとしては、外出は飛散量が多い時間帯を避けましょう。一般に、昼の11~14時、夕方の17~19時頃が多いと言われています。また、外出時には、表面が毛羽だった衣服は避け、帰宅時は花粉を室内に持ち込まないよう、髪や衣服についた花粉をブラシなどで払ってから家に入りましょう。