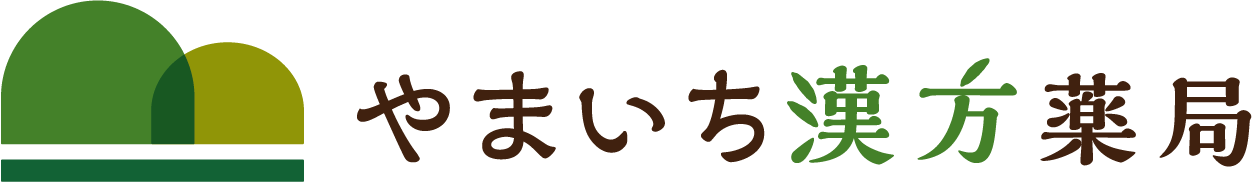こんにちは。
夏の体調不良は、暑さと湿気が主な要因に。厳しい暑さは体力を消耗し、食欲の低下や睡眠不足を招きます。また、屋外と室内の気温差、湿気で汗が蒸発しにくい(体温を下げにくい)などの要因で、自律神経が乱れてしまうことも。こうしたダメージが蓄積されると、疲労感、食欲不振、頭痛といった、いわゆる「夏バテ」不調を招いてしまいます。
一方「熱中症」も、高温多湿の環境に長時間いることで起こる症状。汗をかいて水分や塩分が不足したり、熱をうまく逃がせなくなったことで、体温が上昇し不調が起こります。
中医学でも、夏は「暑邪」や「湿邪」のダメージを受けやすい季節と考えます。暑邪が体に入り込むと、体内に過剰な熱がこもります。すると、たくさん汗をかいて体内の「津液」や「気」を消耗するように。その結果、潤い不足で熱をうまく冷ませない、エネルギー不足で疲れやすい、といった不調が起こるようになります。
また、潤い不足によるドロドロ血で五臓の「心」に負担がかかったり、「湿邪」が「脾胃(胃腸)」の働きを弱らせたりすることも、夏の不調を引き起こす大きな要因となります。
夏は体内の陽気も活発で、暑さの中でも活動的に過ごすことが多い時期。その分、体を消耗して不調を招くことも多いので、体調管理にしっかり気を配りましょう。
「夏バテ」予防の体質ケア
「心」のケア
夏は五臓の「心」がダメージを受けやすい季節。暑さでたくさん汗をかくと、体内の「津液」と「気」が消耗します。すると、潤い不足で血液が濃縮し、心に負担がかかるように。また、エネルギー不足で心の働きが弱くなることもあります。
「心」の不調は体全体に影響するほか、不眠を招いて疲れが溜まりやすくなることも。夏は自然と汗の量が増えます。「心」の働きを守るためにも、不足しがちな「津液」と「気」をしっかり養い、血流の良い状態を保ちましょう。
このタイプの気になる症状として、動悸、息切れ、不整脈、多汗、不眠、不安感、イライラ、頭がボーっとする、胸の詰まり、胸痛、舌の色が淡いまたは暗い…など。
百合根、蓮の実、小麦、鶏のハツ、卵、ぶどう、ライチ、桃、らっきょう、タマネギ、海藻類、梅干し、レモン、トマト、ヨーグルトなど、水分と気を養い、過剰な汗を止める食材を摂りましょう。
漢方では、麦味参顆粒、冠元顆粒、心脾顆粒、婦宝当帰膠、炙甘草湯、西洋人参など。
「脾胃」のケア
「脾胃(胃腸)」は湿気や冷えに弱い臓器。夏は湿度が高く、暑さで冷たい飲食も多くなりがち。すると、「脾胃」が疲れて食欲が落ち、元気の源となる「気」「血」を十分生みだせない状態に。その結果、体のエネルギーや栄養不足で、疲れやすい、だるい…といった夏バテ不調が起こりやすくなります。
「脾胃」の働きを守ることは、夏を元気に乗り切る基本。冷たい飲食はなるべく避ける、刺激物を摂り過ぎないなど、「脾胃」に負担をかけない食生活を心掛けましょう。
このタイプの気になる症状として、夏バテしやすい、疲労感が強い、食欲不振、体重の減少(夏やせ)、下痢、軟便、舌の色が淡い…など。
大豆製品、いんげん豆、米、もち米、豚肉、鶏肉、うなぎ、あじ、山芋、じゃがいも、かぼちゃ、きのこ類など、温性・甘味の食材を摂りましょう。
漢方では、健胃顆粒、健脾散、補中益気湯、六君子湯、清暑益気湯など。
「熱中症」の対処法
過剰な「熱」を冷ます
体に「暑邪」が入り込むと、体内に「熱」がこもります。過剰な「熱」は体の潤いを消耗するため、放っておくと、「津液不足」でさらに「熱」を冷ましにくい状態に。その結果、体温の上昇、のぼせ、発汗といった症状が起こるようになります。
こうした不調を感じたときは、まず体内の「熱」を冷ますことが肝腎。
このタイプの気になる症状として、発熱、顔が赤い、口やのどの渇き、汗が多い、イライラしやすい、怒りっぽい、不眠、舌が赤く舌苔が黄色い…など。
すいか、メロン、苦瓜、冬瓜、きゅうり、トマト、緑茶など、暑邪を払い、過剰な熱を冷ます食材を摂りましょう。
漢方では、牛黄製剤、五涼華、白虎加人参湯、黄連解毒湯など。
「暑湿」を取り除く
蒸し暑い夏は、「暑邪」と「湿邪」が一緒に体に入り込むことも。「湿邪」は「脾胃(胃腸)」の働きを低下させるため、食欲不振や胃もたれなどで夏バテしやすい状態に。こうした夏バテ体質で「暑邪」のダメージを受けると、「熱」にうまく対処できず熱中症を招きやすくなります。
このタイプの養生は、体に溜まった「暑邪」と「湿邪」を取り除くことが基本。体をスッキリさせて「脾胃」の働きを整え、しっかり栄養を摂って体調を回復させましょう。
このタイプの気になる症状として、夏やせ、夏バテ気味、胃もたれ、胃のムカつき、食欲不振、膨満感、下痢、軟便、疲労感、頭が重い、体が重い、舌苔が白いまたは黄色でベタつく…など。
ハトムギ、緑豆、もやし、春雨、冬瓜、海藻類、シソ、ミカンの皮、みょうが、しょうがなど、「湿」と「熱」を取り除き、「脾胃」を整える食材を摂りましょう。
漢方では、勝湿顆粒、健胃顆粒、五苓散、茵蔯五苓散、五行草など。