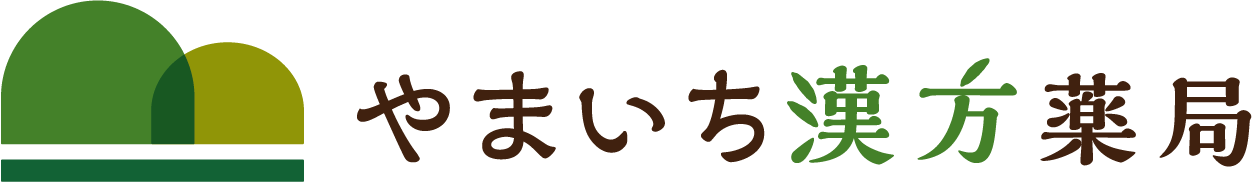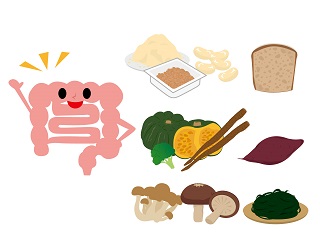こんにちは。
炭水化物の中で、消化吸収できるものを「糖質」、人の消化酵素では消化できないものを「食物繊維」と言い、この「食物繊維」は水溶性と不溶性の2つに分けられます。

水溶性食物繊維
水溶性食物繊維は粘性、保水性があるため、水分を多く吸収して膨潤し、胃の満腹感が得られます。一緒に食べた食物の移動を緩慢にし、糖分やコレステロールを包むようにして栄養分吸収を阻害する働きがあるので、食後の血糖値の上昇を抑え、血中のコレステロールを低下させる効果などが認められています。また、一部は腸内細菌の栄養源になり、短鎖脂肪酸を生成して腸を刺激し、便通を促進します。
- 血糖値の穏やかな上昇
- 脂質異常症の予防
- 腸内の有害物質の排出
- 高血圧、肥満予防
- 発ガン抑制
- 腸内の善玉菌の増加
アガロース(寒天)、アルギン酸ナトリウム(ワカメ、コンブ)、イヌリン(ゴボウ、ダイコン)、β-グルカン(オオムギ、キノコ類)、グルコマンナン(コンニャク)、ペクチン(リンゴ、モモ、イチゴ)

不溶性食物繊維
不溶性食物繊維は、口から摂取した後は、そのまま大腸まで運ばれて便の量を増やすことで腸壁を刺激して排便を促進します。適量の摂取は腸内環境を整えて大腸がんを予防し、さらに肥満、Ⅱ型糖尿病(肥満・運動不足・ストレスなどをキッカケに発症する糖尿病)や心臓病のリスクを低下させます。
- 便の量を増やす
- 便秘の予防、解消
- 腸内の有害物質の排出
- 腸内の善玉菌の増加
- 肥満の予防
キチン(エビ、カニの殻)、セルロース(野菜、穀物)、ヘミセルロース(野菜、豆類、穀物、海藻類)、リグニン(野菜、豆類、穀物のふすま)
ひと昔前は日本人の食生活は穀物や野菜が豊富で、食物繊維の摂取量も十分でした。しかし、食生活の欧米化から最近では明らかに食物繊維不足。健康維持のため、水溶性食物繊維、不溶性食物繊維の両方を積極的に摂りましょう。